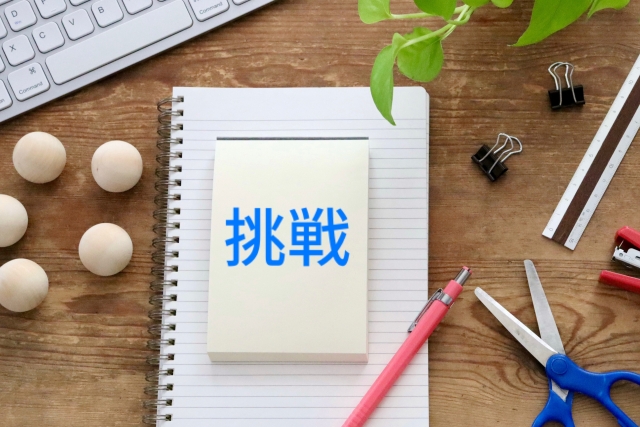
目次
初めに
今回のコラムでこの長かった創業者向けのコラムの最後となります。最後は、創業後に何を行うべきなのかということと、顧問税理士は必要なのか、顧問税理士にどのような税理士を選ぶべきなのかについて述べていこうと思います。
創業後には、開業届などを税務署に提出するなどの書類関係の作業なども多くありますが、今回はその部分については割愛します。理由としては、顧問税理士を付けるときに大抵の税理士事務所で行ってくれますので、今回のコラムからは除きます。
では、今回のコラムで何を話すかというと、創業後に経営を行っていくためにどのようなことをする必要があるのか、どのような資料が必要になるのかというところと、顧問税理士を付ける必要があるのか、どのような税理士を選ぶべきなのかについてになります。
創業後の経営については、今までのPartの話と重なる部分が多いので、主に顧問税理士の部分の話になるかと思います。
創業後に行うこと
創業後に行うことは多岐にわたると思います。このコラムだけでは書ききれませんし、事業によって対策なども変わってくるでしょう。そのためこのコラムでは全ての事業・全ての業種に当てはまるようなものに焦点を当てようと思います。
①資金繰表
まずは、資金繰表です。これは必ず作るようにしてもらいたい資料の1つです。創業計画の際にも資金繰表は作成してもらいましたが、創業後の方がもっと重要になってきます。なぜなら、創業後は必ず成長もしくは衰退をするからです。成長の時にも資金繰りは厳しくなります。特に急成長をした場合には、資金繰りが支出に追いつかないということも多々あるからです。
このように、創業後の方が資金繰表は大切になります。少なくとも6カ月先の分までは作成するようにしておきましょう。6カ月先に資金がなくなるようであれば、追加融資を考えたり、売上や仕入の内容を見直す必要があるかもしれません。
そして、創業後の資金繰表は将来の予測だけでなく、過去の実績についても記載していくのがいいでしょう。つまり、予測と実績との差異を分析していくことになります。これが創業後ずっと大切になってきます。
資金繰表の作り方には初めのうちから慣れておきましょう。融資をする際には必ず必要となってくるものになります。資金繰表を見るっことによって、無駄遣いをしていないかなどの抑止にもつながります。創業後は反省をする機会を設けないと、経営に忙しく中々そっちの方まで手が回らなくなってきます。資金繰表を毎月作ると決めておけば、月に1回は反省と次への対策を設ける機会を作ることが可能になります。
融資の面や経営の面でも便利となってくるのが資金繰表です。創業の際に作って作り方を忘れない間に、創業後も作り続ける癖をつけましょう。
②経営計画書
続いては経営計画書です。これも創業計画書と似ているものになりますが、もっと戦略的なものとおもってもらえればいいでしょう。経営計画書を作成している中小企業は全国でも10%程度といわれています。
ハッキリいうと経営計画書を作るのは面倒でしょう。経営計画書がなくても成長している企業もたくさんありますから。しかし、ないよりはある方がいいに決まっています。なぜなら経営計画書というのは経営者の意思表示であり、経営戦略になるからです。経営計画書として文章にすることで、従業員にも伝わりやすくなりますし、銀行にも説明をしやすくなります。
経営計画書とは経営の道しるべ的な存在でしょう。どこを目指しているのか、何を目標にしているのか、どのように達成していくのかということを書いていくのが経営計画書になります。
さらに経営計画書を作成することは、銀行融資でもプラスにつながります。そりゃそうですよね。文章として目標・未来を示してくれているわけですから銀行としても分かりやすくていいでしょう。社長から聞き出す手間も省けるわけですから。
経営計画書と言って難しく聞こえるかもしれませんが、難しく書く必要はありません。Part1・Part2でも説明していきたことを書けばいいのです。
「だれを」「なにを」「どこで」「どのように」この戦略を今後どうしていくのか、そしてその先の利益計画はどうなるのかということを書いていくのです。創業計画書の戦略部分だけを抜き出した形と思ってもらえればいいでしょう。
何もかっこよく、難しく書かなくてもいいのです。経営者が考えていること目標としていることを、従業員や銀行、取引先に分かってもらうということが大切なのですから。
そう思えば難しくないでしょう?難しく書かなくても、書いている企業は10%に満たないんですから、圧倒的アドバンテージになります。どのような未来を想像しているのか、どのような企業の将来を描いていくのかを経営計画書として書き出していきましょう。
この経営計画書についても毎年書くように癖づけてください。そして、経営計画発表会なんてものも開催できるとさらに良いかもしれませんね!
③数字に強くなる
経営者には数字に強くなってもらいたいです。経営者の中には数字が苦手という方もいますが、数字が読めないと経営者は務まりません。苦手でも強くなってもらいたいと思います。得意になる必要はありませんし、税理士や会計士のように全てを理解する必要はありません。ポイントポイントを押さえてもらえれば十分です。大事なのは、数字から逃げないということ、必ず数字を見るということ、数字に慣れるということです。
創業後は必ず、決算の数字を見てください。毎月の試算表の数字を見てください。数字を見ない経営者は経営者失格だと思います。経営は全て数字に表れます。
このコラムでは詳しい説明はしません。初めのうちは抵抗があるかもしれませんが、経営者は数字に慣れるようにしてください。
ここまでの3つが創業後にも行ってもらいたいことになります。資金繰表や経営計画書や数字など嫌なこと面倒なことが多いかもしれませんが、それが経営です。経営者の仕事です。経営者は考えることと選択すること、判断することが仕事です。作業することは経営者の仕事にはなりません。
そのため、創業後に経営者となられる創業者のみなさんには経営者として、考えることや選択、判断することに集中してもらえるようになってもらいたいと思います。
創業後に顧問税理士は必要か
次に、顧問税理士の話に移ろうと思います。創業した後に顧問税理士を付けるべきなのかどうなのかを迷われる方は多いでしょう。
結論としては、顧問税理士を付けてもらうべきだと思います。特に法人で創業される方については顧問税理士は必須と考えてもらっていいでしょう。たまに、法人でも顧問税理士を付けていないという方もいますが、非常に危険だと思います。実際問題は、税理士がいなくても自分自身で申告をしても構いませんので、法律上の問題はありません。しかし、法人となると個人事業主と比べて、経理処理も複雑になりますし、決算申告も複雑になりますので税理士との契約はしてもらうのがいいでしょう。
個人事業主の方については、規模にもよりますが自分自身で十分行うことは可能だと思います。初めの方は苦労するかもしれませんが、規模が大きくなるまでは顧問税理士を付けなくても問題はないかなと思います。つけてもらう方が確実ですけどね。
顧問税理士を付けていない方が顧問税理士を付けようと決めるタイミングは、だいたい決まっています。税務調査が入るときもしくは、入ったあとです。
法人・個人両方とも初めての申告をするときは、ドキドキするのですが意外とスムーズに受理されるので、自分でできるかもと思ってしまうのでしょう。もしくは、税理士に対する報酬がもったいないと思うのでしょう。
そして、成長していくにつれて経理処理が雑になったり、申告が適当になってきたときに税務調査が入り、何百万という追徴課税を受けるということが良くあります。このタイミングで顧問税理士を探すという方が多いように思います。
よく、税務調査が入るという電話が来たので対応してくれますか?という相談もあるのですが、顧問契約を結んで毎月顧問先の情報を見ていないと税理士は何もわからないので対応できません。税務署の言われるがままにするしかないことがほとんどです。電話が来た時点で調査が始まることになります。重加算税を回避するために修正申告を出すぐらいでしょう。
そうなる前に税理士と顧問契約をしてもらうことがいいでしょう。税務調査が入ってからでは遅いですから。
理想は、創業時から顧問契約を結び経理処理や書類の保存方法などを税理士と相談しながら、体制を整えていくことだと思います。
税理士報酬をもったいないと考えている方もみかけますが、調査で何百万ととられるくらいなら税理士報酬を払って、しっかりとしておいてもらう方がリスクヘッジになるのではないかと思います。税理士がいるから税務調査が入らないわけではないですし、税務調査で追徴課税されないわけではないですが、少なくともリスクは減らすことができます。
税理士に対する報酬は「費用」ではなく「投資」です。みなさんも投資だと思えばもったいないと思うことはないのではないでしょうか?しかし、全ての税理士が「投資」になるかというとそうではありません。しっかりと自分がしてもらいたいことと、税理士ができることを見極めて顧問契約を結ぶ必要があります。
次では、どのような税理士がいるのか、どのような税理士を付けるべきなのか、どのように税理士を選ぶべきなのかについてお話していきましょう。
顧問税理士について
⑴どのように税理士を選ぶべきなのか
まずは、どのように税理士を選ぶべきかについて考えていきましょう。
この後に、どのような税理士がいるのか、どのような税理士を付けるべきなのかを考えていきます。
税理士といってもそれぞれです。かなり多くの税理士事務所が日本にはあります。検索するだけでもヒットする数も多いのではないでしょうか。
では、どのように税理士を選ぶべきなのか。
①税理士報酬だけで決めてはいけない
これは絶対です。税理士報酬が安いからという理由だけで選んではいけません。前回も言いましたが、税理士報酬は「費用」ではなく「投資」と思ってもらいたいです。報酬額を安いかどうかで決めるということは、税理士報酬がもったいないと思っているのではないでしょうか?
確かに税理士報酬は毎月かかりますし、年間にするとそれなりの金額になると思いますが、報酬額が安いからという理由で探すのは辞めましょう。
後で後悔することが多いと思います。
②税理士に何をして欲しいかを決める
そして、これも大切になってきます。税理士に何を求めるかです。税理士といっても税理士業務は幅広いため様々な税理士が存在しています。そんな中、どのような業務を税理士に求めるかを決めておくことが大切です。例えば、「何が何でも安く申告をしてもらいたい」でもいいですし、「申告だけでなく経営のアドバイスをもらいたい」でもいいですし、「税金が高くなってきたから節税の方法を教えてもらいたい」でもいいでしょう。何を税理士に求めるかを決めてもらうことで、税理士を選びやすくなると思います。
⑵どのような税理士がいるのか
続いて税理士にはどのような税理士がいるのかについてです。
そもそも税理士になるためには大きく分けて3つの方法があります。
①税理士試験に合格する(大学院の免除を含む)
1つ目は税理士試験に合格して税理士になる人です。税理士試験は13科目のうち5科目に合格する必要があります。いくつかは必須科目なので必ず取らないといけないのですが、この試験の制度が税理士の専門分野を作ることになります。
13科目のうち5科目ですので、8科目については勉強をしていないということになります。つまり、税理士の中には知らない分野もあるということです。それをまず理解してもらうのがいいでしょう。
そして、試験合格には大学院免除というものもあります。大学院免除とは簡単にいうと、5科目のうち2科目を免除されるというものです。つまり、大学院免除をしているとさらに試験勉強をしている科目は少ないことになります。
このように税理士には得意分野・専門分野があるということです。
②税務署出身
2つ目の税理士のなり方が税務署に一定年数勤務した後に研修を受けることで税理士なる方法もあります。いわゆる「税務署あがり」や「国税OB」と言われる税理士です。税務署出身の税理士の方の特徴としては、税務調査のイロハを知っていることが大きいことだと思います。だからといって、税務調査が来ないわけでもありません。さらに、税務署のどの課にいたかによって得意な業種がわかれることになります。ここでも専門分野があるということです。
③公認会計士・弁護士
そして3つめは公認会計士もしくは弁護士の資格をもっている人も税理士資格を取ることができます。試験を受けずにとることができます。ダブルライセンスになりますので、税理士業務だけでなく、会計士業務や弁護士業務を行うことができるのも強みです。ただ、税理士試験を受けていないということと、人によっては税理士事務所に勤務していた経験がないことから、実務面の見分けが必要となってくるでしょう。
このように税理士になるためには3つの方法があります。全ての方法で良い点悪い点はありますし、その方法で税理士になっているから良い悪いがあるわけではありません。
分かってもらいたいことは、税理士には様々な方法で税理士になっている人がいるということと、税理士それぞれに専門分野があるということになります。そのため、自分自身が税理士に何を求めているかを決める必要があります。
ここでは、どうのような税理士がいるのかについて、税理士になる方法から見てきました。次に税理士がどのような業務ができるのかを見ていきます。一部だけになりますので、探せばもっと色々なことをしている税理士がいると思ってもらっていいでしょう。
⑶税理士が行う業務とは
税理士の業務について簡単に説明しようと思います。ここに書いてある以外にも様々な業務を行っている税理士の先生方がいますので、自分が求めている業務を行ってもらえる税理士の先生を探してもらうのがいいでしょう。
①税務申告・税務相談(節税など)
まずは、税務申告・税務相談です。ここは専門分野はありますが、ほとんどの税理士事務所が行っているでしょう。主な専門分野分けとしては、法人・個人・相続にわけられると思います。特に相続については、専門の税理士に頼むのがいいでしょう。
②記帳代行
次に記帳代行です。税理士と言えば、申告と記帳代行のイメージの方も多いでしょう。これも多くの税理士事務所が行っています。記帳代行を受けていないというところもありますので、相談してもらうのがいいでしょう。
記帳代行についての私の考えは、記帳代行はせず自計化できるようにしましょう。
健康で自分の体は自分自身で管理するのと同じで、会社の財務は会社の健康と同じですから、会社自身で管理できるように自計化をすることをおススメします。
③税務調査対応
そして、税務調査対応です。顧問契約を結んでいれば間違いなく対応してくれると思います。費用面については、税理士事務所の契約次第だと思いますが問題なく対応してくれるでしょう。顧問契約を結んでいない方の税務調査については税理士事務所次第だと思います。費用面でも高くなりますし、対応してもらっても知らないことは知らないと言うしかないので、対応してくれるからといって大きな期待はしない方がいいでしょう。
ここまでの①~③については、ほとんどの税理士事務所でおこなっていると思います。次の④からは税理士事務所の特徴(差別化のポイント)ともいえるものになってくるでしょう。
④クラウド会計の導入
クラウド会計は最近よく聞くのではないでしょうか?「freee」や「マネーフォワード」などですね。これらのクラウド会計のニーズは高まりつつあります。しかし、クラウド会計の導入ができる税理士というのは意外と少ないものなのです。クラウド会計を導入したいということであれば、クラウド会計に対応できる税理士を検討しましょう。
⑤資金繰りなどの支援
資金繰りの支援です。経営者の方にとって悩みの種となるのが資金繰りではないでしょうか。税理士によっては、資金繰りの支援を行ってくれる税理士も数多くいますので、一度相談してみるのがいいでしょう。
⑥銀行融資
資金繰りと近いところで銀行融資です。銀行融資の支援を行ってくれる税理士います。銀行融資などで困っていることがあれば、税理士に聞いてみるのもいいかもしれません。税理士の先生によっては金融機関を紹介してくれるかもしれません。
⑦経営コンサルティング
この分野を行ってくれる税理士は貴重です。経営者とともに経営について考えてくれ、アドバイスをくれる税理士と思ってもらえればいいでしょう。中小企業経営者の相談相手の1位は税理士なのですが、この分野を得意とする税理士は意外と少ないと思います。
このほかにも税理士によっては様々な業務を行っています。
自分自身が何を税理士求めているかを決めてもらうことが大切というのは、このような理由からです。税理士の業務の範囲が多いため、税理士によってはできない業務や苦手としている分野があったりします。初めの契約の段階でしっかりと、何をしてほしいのか何を求めているのか、逆に税理士が何をできるのかを聞いておくことがいいでしょう。
それらを総合して税理士を選んでもらうのがいいと思います。
税理士の報酬が安いかどうかだけで決めてしまうと、経営者自身がしてもらいたい業務をやってくれないなどと不満を持つことになることが多いと思います。
⑷税理士についてのまとめ
ここまで税理士について述べてきました。長くなったので短くまとめましょう。
まず、創業時から税理士と顧問契約をした方がいいです。特に法人で設立する場合には顧問契約をするようにしましょう。
そして、税理士の選び方は
- 値段で決めるのではなく、自分自身が求めている業務内容で決める
- 税理士には様々な方法でなっている人がいる、専門分野がある。
- 何ができるか・得意か税理士の業務内容について聞く。
この3点について覚えておいてもらえれば問題ないでしょう。必ず良い税理士に出会えると思います。
もし、顧問契約をした税理士が自分が思っていた税理士と違った場合には、すぐ違う税理士を探しましょう。よく税理士を変えない経営者の方がいますが、税理士側としては変わられることは特に何とも思っていません。守秘義務がありますから、情報が洩れるということもありませんので、変えたいと思えば変えてもらうのがいいでしょう。
さらにセカンドオピニオンという考え方もあります。医者と同じように税理士もセカンドオピニオンを付けるのです。様々な理由で既存の税理士を変えにくいという方については、セカンドオピニオンで税務相談・節税アドバイスを求めることができるのでいいと思います。
税理士によって、会社に大きな影響(いい意味でも悪い意味でも)がありますので、税理士の選択は慎重に行いましょう。
全章まとめ
今回のコラムまで、9月1カ月にわたって創業者向けのコラムを書いてきました。創業前に考えることから、計画書の書き方や資金繰り表の書き方、創業融資、そして創業後に必要なことや税理士の考え方まで広範囲にわたると思います。創業は事業の始まりですので、とても大切な時期だと思います。考えることが多くて大変だとは思いますがこのコラムを読んで創業期を充実にしてもらい、創業を行っていってもらいたいです。そして企業を成長させて目標の達成をしていってもらいたいです。
私たちの事務所でも創業・起業支援プランとして創業者・起業者の方を創業時から経営のパートナーとしてサポートを行っています。
気になる方は、お問い合わせください。
