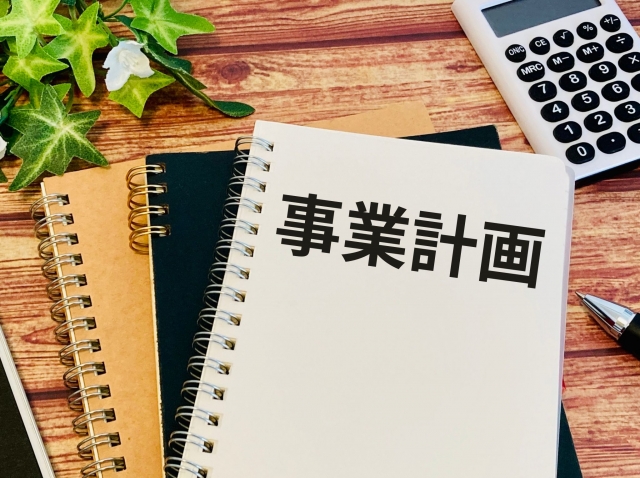
目次
初めに
Part3では日本政策金融公庫の創業計画書の書き方を説明してきました。今回のPartでは、私たちの事務所であるトラストソルコンサルティング(東憲吾税理士事務所)が使用している創業計画書の書き方について紹介します。大部分は日本政策金融公庫の創業計画書の書き方と似ているので、同じ部分の説明は大幅に省略しようと思います。
日本政策金融公庫の創業計画書との違いとしては、より詳細に記載していくという形になります。ですので、私たちの事務所の創業計画書を作成してから、日本政策金融公庫の創業計画書を作成してもらうと作成しやすいかもしれません。
それでは、紹介の方に進みましょう。資料をダウンロードできるようにしておきますので、ダウンロードして自由に使ってください。
コラム自体は文字ばかりになってしまいますので、資料を用意していただき読んでもらいながら作っていくのがいいでしょう。
↓資料ダウンロードはこちらから↓
トラスト流創業計画書
トラスト流の創業計画書は1ページに収めるのではなく、数ページにわたって作成してもらいます。①事業概要・プロフィール②SWOT分析・競合分析③事業コンセプト④資金計画⑤損益計画⑥アクションプラン⑦損益計画表(利益計画)⑧資金繰表という構成になっています。
①~⑤までは日本政策金融公庫の創業計画書を詳細に書いていく形になります。⑥~⑧はさらに表という形で具体的にしていく形になります。⑦⑧は次回コラムの利益計画の部分で解説をしていこうと思いますので、今回のコラムでは省略します。今回のコラムでは、①~⑥までを説明していきます。
①事業概要・プロフィール
ここの部分は、日本政策金融公庫の創業計画書と比較的似ています。
事業概要の部分では、開業の形態(個人か法人か)、資本金(法人の場合)、業種など少し詳しい内容まで書くかたちになっています。
プロフィールの部分は、日本政策金融公庫のプロフィールよりも書きやすいように枠が大きくなっています。書く内容としては、ほぼ同じなので省略します。
ここのページは、創業の目的や動機、自分自身の経験の洗い出しをしてもらう形になります。
②SWOT分析・競合分析
ここは日本政策金融公庫の創業計画書よりも具体的に書いてもらうことになります。
まずは、SWOT分析です。Part1・Part2でも書きだした内容を書いてもらえれば大丈夫です。少し名称が変わっているだけで、強みと弱みを内部環境分析として⒊に書いてもらいます。追い風となっていること(機会)と懸念されていること(脅威)については外部環境分析として⒋に書いてもらいます。ここまではSWOT分析ですので、すでにPart1などで出来上がっているものを書いてもらえればすぐにできると思います。
次は、競合分析になります。
創業しようとしている業種の競合となる先を分析してみてください。差別化戦略・ニッチ戦略をとるために必要なのが、競合分析になります。同じような業種がいる場合といない場合では戦略が大きくことなってくると思います。自分の競合となる先はどのような先になるのかを分析してみましょう。
飲食店の場合には、実際に食べにいってもいいでしょう。製造業や建設業のように試すことができない場合に、ホームページや口コミなどを参考に分析してみましょう。
③事業コンセプト
ここの部分は日本政策金融公庫の部分と重なる部分が多いです。
⒌事業コンセプトでは、「だれに」「なにを」「どのように」を書いてもらいます。つまりランチェスター戦略で考え抜いたものを書いてもらえれば大丈夫です。
⒍事業内容では、商品・サービスの売上高や割合について書いてもらい、取引先条件については日本政策金融公庫の取引先と同じ内容になります。従業員・人件費の部分ついても同じです。
④資金計画
この部分も日本政策金融公庫の「必要資金と調達方法」の部分について書きやすいようにしています。
書き方の手順は、Part3で説明したものと同じなので省略します。変わっている部分だけ説明します。
⑴必要な資金
まずは必要な資金についてです。この部分は日本政策金融公庫の「必要な資金と調達方法」と異なる箇所があります。
設備資金
設備資金の部分については、店舗関係(土地や改装費・保証金)と什器・備品、その他の3つに分けています。製造業での機械装置については、店舗関係に含んでもらえば大丈夫です。また、業種によって項目の名前は変えてもらっても問題ありません。好きなように分かりやすいように名称は変えてもらって構いません。
イメージとしては、店舗関係は償却期間が長いもの(数十年使えるもの)や金額が大きいもので、什器備品などは償却期間の短いもの(数年間で買い替えるもの)や金額的に少額なものと思ってください。
運転資金
運転資金については、諸経費と販促関係に分けています。諸経費の〇月分のところについては、3カ月~6カ月を目安に書いてください。あまり大きすぎても意味がありませんので、創業するまでの期間+創業から3カ月くらいの想定でいいでしょう。
販促関係
そして、販促関係です。これが非常に重要です。売上を上げるために必要な販促費をここで考えておきます。販促関係とは、HP代や名刺代、広告宣伝費などをいいます。売上を上げるため知名度を上げるために必要なものをピックアップし、さらに金額もいくらまで掛けることができるかを想定しておきましょう。
この販促関係は抜けてしまうことが多いので、運転資金の中に別枠で記載している形になります。ホームページについては、今の時代にはなくてはならないものになるでしょうし、インスタグラムやグーグル検索に優先的に表示してもらうためにも広告費はかかります。いくら掛けるというよりも、いくらまでなら掛けられるとい考え方の方が大事だと思います。広告宣伝費は掛け始めるといくらでもかかってしまうからです。
広告宣伝費は必ず創業した後にかかってくるものになりますので、初めの間から計上しておきましょう。
⑵調達の方法
調達の方法については、日本政策金融公庫のものと考え方は同じですので、自己資金から順番に記載してもらえれば大丈夫です。項目が少し細かくなっているだけになります。
⑤損益計画
この部分も日本政策金融公庫の事業の見通しの部分を細かく詳細にし、さらに借入金の返済と生活費(個人事業主のみ)を追加した形にしています。
売上高と原価の部分は変わらないので説明を省略します。
経費の部分については、かなり細かく書けるようにしています。日本政策金融公庫の場合は、人件費・家賃・利息だったものを、水道光熱費や諸会費、広告宣伝費など、事業でかかってくるであろうものを自由に記載できる形にしています。重要なものだけを追加して書いてもらえれば十分です。注意としては、細かく神経質になりすぎないことです。だいたいこれくらいかな?と思って書いてもらえれば十分でしょう。
利益のここまでは日本政策金融公庫の事業の見通しと同じです。
ここから先の2つが追加事項になっています。
⑴借入金返済
ここは借入金の元本部分になります。
借入金の総額を返済期間の総月数で割ってもらえれば元本がいくらかでますので、その金額を記載してください。
⑵生活費
生活費は個人事業主のみ使用します。理由としては、個人事業主の場合には法人の役員報酬のように代表者への給料という概念がないためです。そのため生活費にいくら必要なのかを把握しておくことが大事になります。
個人事業主の場合は、利益の中から生活費を捻出することになるためです。
⑶余剰金
利益から⑴借入金返済と⑵生活費を引いた残りが余剰金になります。これがお金として残る部分になります。ここがプラスになって初めてお金がたまっていくことになるのです。
ここがプラスになるように頑張りましょう。創業当初はマイナスになるかもしれませんが、軌道にのった後にはプラスになるように、さらにはもっとプラスになるように努力していきましょう。ここもプラスにしてお金を残していくことが経営になります。
⑥アクションプラン
ここから先が独自の創業計画書になります。
まずは、アクションプランです。アクションプランとは創業までの行動計画書(創業後も書いてもらって構いません)と思ってください。何に何カ月かかるかを書き出します。
これを作成することで行動が見える化されるために、もう少し急いだほうがいいや、もう少し時間があるためゆっくり考えようなど立ち止まるきっかけにもできます。
書き方としては、まず左の「項目」に行動を書きます。
例えば、店舗の改装をする場合には「店舗改装」と書きます。
そして、各月の「上旬」「中旬」「下旬」のくくりで何をするのかを書き矢印で引っ張ります。
例えば、6月上旬「打ち合わせ」、7月上旬「見積完成」、7月中旬「契約」、8月上旬~9月下旬「改装工事」みたいな感じです。
このように創業までの行う行動を全て書いてみてください。整理されるために行動に移しやすくなります。また、空いている時期がわかるため空いている時期に違う行動を埋めるなど効率化にも使えます。
一度書き出してみて、忙しすぎたり時間が空きすぎるようであれば修正を加えるなどして、創業までに間に合うように行動プランを作り上げてみてください。
まとめ
以上が私たちの事務所で使用している創業計画書の①~⑥までの書き方になります。⑦⑧については、次回のコラムで利益計画と合わせて解説していこうと思います。
いかがでしたか?日本政策金融公庫の創業計画書と比較的似ている部分もあったと思います。日本政策金融公庫のものよりも詳細に書けるようにしていますので、私たちの創業計画書を使ってもらう方が、無理に纏める必要がないので初めは書きやすいのではないかと思います。
日本政策金融公庫へ融資の依頼をする際も、日本政策金融公庫の資料を使わないといけないわけではありませんので、私たちの創業計画書で提出してもらっても問題はありません。アクションプランや利益計画・資金繰表まで作成をしているので、むしろ喜ばれるかもしれませんね。おそらく融資を受ける際に聞かれる、もしくは提出を求められる資料になりますので、創業計画書の段階で作っておけば二度手間を省くこともできます。
今回は創業計画書として創業時の計画書でしたが、経営を行っていくうえでは毎年のように経営計画書を作成していくことが望まれますので、計画書の作り方は覚えておいて損はないでしょう。特に次回コラム以降に解説する利益計画と資金繰表については、創業時以外の融資でも必要になってきますので、ぜひ覚えておいてください。
