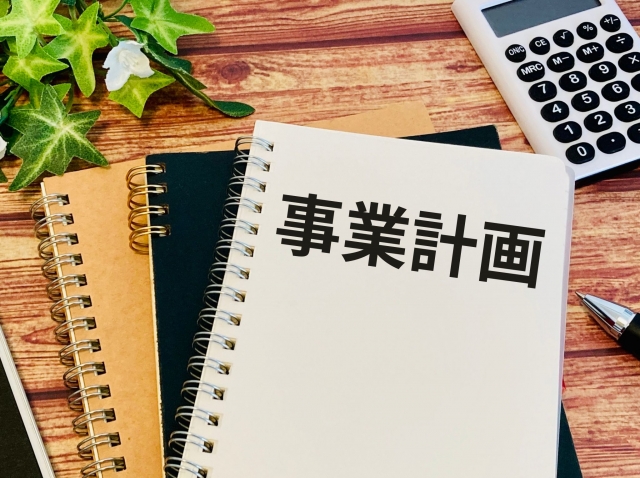
目次
初めに
前回までのコラムでは、創業前に考えておくべき内容について解説しました。「なぜ」から考えて、「何を」「誰に」「どこで」「いつから」「どのように」と理念から商品・サービス、戦略の考え方について考えてきました。今回のコラムからは前回までに考えたものを実物にしていく段階になります。今は、メモ書きのような段階でしょう。これを言葉・文章にしていくのが今回からのコラムとなります。
まずは、創業計画書の作り方からです。まずは言葉で計画書を作ってもらいます。細かい利益計画は次のコラムで説明します。今回の創業計画書は、日本政策金融公庫の創業計画書と、私たちの事務所で使用している創業計画書の2つで説明していこうと思います。
理由としては、日本政策金融公庫の創業計画書は綺麗にまとめられすぎているためです。まとまりすぎて書きにくいということもあるでしょう。そこで、私たちの事務所で使用している創業計画書での作り方も合わせて解説しようと思います。
日本政策金融公庫の創業計画書と私たちの事務所の創業計画書ともに、最後にダウンロードできるようにしておきますので自由に使ってください。
日本政策金融公庫の創業計画書の書き方
まずは、日本政策金融公庫の創業計画書の書き方から説明していきます。
日本政策金融公庫の創業計画書を開けて読んでいってもらえれば書きやすいと思います。
項目としては、①創業の動機②経営者の略歴③取り扱い商品・サービス④従業員⑤取引先・取引関係等⑥関連企業⑦お借入れの状況⑧必要な資金と調達方法⑨事業の見通し⑩自由記述欄になります。
それでは1つずつ簡単に説明していきましょう。
①創業の動機
まずは、創業の動機です。なぜ創業するのか、なぜ創業したいのか。理念や目的になります。そう、Part1の時に考えてもらった「なぜ」の部分ですね。「なぜ」の部分を文章として書いてもらえれば完成です。最初に考えてあったものなので楽ですね。
②経営者の略歴等
ここは創業者ご自身のことになります。いままでの職業経験や身に着けた技能、持っている資格についてありのままに書いてもらえれば大丈夫です。
内容の部分については、就職していた先でどのような担当をしていたのか、どのような技術を身に着けたのか、どのようなことを学んだのかを書いてもらえれば十分でしょう。就職だけでなく、アルバイトやパートの時代でもいいと思います。
就職経験がない方や就職先以外でも学んでいた方の場合には、学生時代に学んでいた分野であったり、専門学校で学んでいたことを書いていただいてもいいでしょう。
大事なのは、創業を考えている事業と今までの経験がどのような関係性があるかということだと思います。就職していた業種と全く違う業種で創業するということもあると思いますが、ある程度過去のどこかで学んでいたり、身に着けていることだと思います。
③取扱商品・サービス
⑴事業内容
事業内容は、どのような事業を行うのかを書いてもらえれば大丈夫ですが、なるべく詳しめに書いてもらう方がいいと思います。
例えば、「コンサルティング業」と書くだけよりも、「建設業の資金繰り改善に特化したコンサルティング業」のようになるべく詳細に書いてもらった方がいいと思います。
⑵取扱商品・サービスの内容
ここは商品のラインナップを書いてもらえればいいでしょう。複数商品がある場合の、売上シェア(売上の比重)も大体の予想で書いてもらえればいいと思います。
⑶単価等
客単価(飲食業や小売業)は想定している客単価を書いてください。客単価とは、お客さん1人が1回に払ってくれる金額になります。
例えば、ラーメン屋で1人は1,500円の会計、もう1人は1,000円の会計だった場合、平均客単価は1,250円になります。
このように自分が1人のお客さんに対して1回いくら払ってくれることを目標にしているかの金額と思ってもらえればいいでしょう。
受注単価(建設業・製造業・サービス業)についても、1回あたりの受注額のレンジ(幅)を書いてもらえれば大丈夫です。
例えば、塗装業の場合だと家一軒を塗る金額の範囲を想定している金額で書いてもらえれば大丈夫です。ここの金額の幅は大きくなってしまっても仕方がないでしょう。自分がターゲットにしている金額幅を書いてもらえればいいと思います。
営業日数・定休日・営業時間(飲食業・小売業)については、想定しているものをそのまま書いてもらえればいいでしょう。例えば、毎週日曜日休みで考えているのであれば、営業日数は26日で、定休日は日曜日と書いてもらえればいいと思います。年中無休であれば年中無休と書いてもらえればいいでしょう。
⑷セールスポイント
ここは自社の強みになります。Part1・Part2で考えてきた、商品・サービスの「強み」を書いてもらえれば大丈夫です。ここは、無理に文章にする必要はないと思います。箇条書きでもいいので「強み」が何なのかをわかるように書いてもらえればいいでしょう。
⑸販売戦略
ここは、「だれに」「どこで」「どのように」です。Part1・Part2でここも考えてきましたね。その「だれに」「どこで」「どのように(戦略)」を書いてもらえれば大丈夫です。
ここも無理に文章にする必要はないと思います。
「だれに」「どこで」「どのように」を箇条書きで書いてもらえれば十分でしょう。
⑹競合・市場など自社を取り巻く環境
ここは、SWOT分析の「脅威」と「機会」の部分になります。Part1の時に考えてもらっていると思いますので、そのときの内容を書いてもらえれば十分でしょう。
ここの部分については、ほぼPart1・Part2の内容をそのまま書く感じではないですか?
Part1・Part2で頭の中を整理しておくことで、創業計画書を書くのが楽になってくるのがわかると思います。
④従業員
ここは予定している従業員を書いてもらえれば大丈夫です。役員(法人のみ)は登記されている役員数を書いてもらえればいいでしょう。家族従業員は、役員の家族の方に働いてもらう場合・個人事業主の家族の方に働いてもらう場合にその人数を書いてもらえればいいと思います。
従業員を雇う予定がない方は、0人でも問題ありません。必ず雇わないといけないことはないです。
⑤取引先・取引関係等
ここには、販売先・仕入先・外注先それぞれの得意先があれば得意先を記載してもらえれば大丈夫です。例えば、元勤務先の会社から仕事を受注できるようであれば、その会社名を書いてもらえればいいですし、飲食店や建設業のように相手が一般消費者の場合には「一般消費者」と書いてもらえれば大丈夫です。
ここで大事なのは、掛取引の割合と、手形の有無、サイト(入出金までの日数)になります。なぜこれらが大事かというと資金繰りを考える際に重要になってくるからです。
例えば、現金商売であれば、売った時に現金が入ってきて、払う時に現金が出ていくためズレが生じませんが、掛取引がある場合にはサイトによって入出金にズレが生じるためです。この把握は利益計画や資金計画の上でも非常に重要になってきます。
例えば、入金サイトが30日・支払サイトが15日の場合を考えてみましょう。
サイトというのは、入金・出金されるまでの期間(日数)と思ってください。
6月末締めの売上が100万円あるとします。その売上の入金はサイトが30日なので、7月末に入金されることになります。
それに対して、6月末締の支払50万円は、サイトが15日のため7月15日に50万円支払必要がでてきます。しかし、入金は30日なので支払う時にお金がないことになりますよね?これが資金繰りになります。
つまり、それぞれのサイトを把握していないと、支払が必要な時にお金がなく払えない状態になる可能性があるということです。このサイトによるズレを運転資金の借入などによって補填していくのです。
ここの欄では、販売先・仕入先・外注先があるかどうかも大事ですが、それよりも掛取引きの割合や入金・出金サイトの方が大事になります。ここを把握することが大切です。
⑥関連企業
ここは、子会社がある場合や逆に親会社がある場合などに記載してもらえれば大丈夫です、ない場合には空白でも問題ありません。
⑦借入状況
ここの部分は、今回の創業にかかるもの以外の借入がある場合に書いてもらえれば大丈夫です。法人の場合は、代表個人としてある借入を書いてもらえればいいです。
多くは、住宅ローン・カーローン・教育ローンがほとんどではないかと思います。現時点(創業計画書作成時点)での残高と、それぞれの返済額を書いてもらえれば問題ありません。返済額については、元本ベースであることが望ましいと思いますが、わからない場合は、利息込みでの年間額でも問題ないでしょう。
⑧必要な資金と調達方法
⑦までは基本的にある情報を書いていくだけですので、比較的簡単だったと思います。
ここからが創業計画書の本題です。実際のお金・融資の部分になってきます。
⑴必要な資金
まずは、左側の必要な資金から埋めていきましょう。
⑴-①設備資金
まずは、設備資金です。ここに創業に必要な設備を全て書き出してみてください。
設備とは、建物や土地(購入する場合)・改装費・機械・備品(机とかなど)・事業で使う車両などを書きだしてください。
ここに記載する金額については見積書ベースで書くのがいいでしょう。見積もりを取ってから書いてもらうことが望ましいです。ここに書いて金額から変動してはいけないことはないので、まずはある程度の見積書でいいでしょう。価格変動で見積もり額に変動がある場合があるので、少し多めに見積もっておいてもらうのがいいかもしれません。
ネットで買う場合には、そのサイトのページをコピーしたり、スクショをしておいてもらうのがいいと思います。見積書については必ず提出を求めれますので。
この設備資金の部分を書き出すところが一番時間を要します。見積もりを取る必要があるためです。見積もりを取るということは、場所も決まっていることになるでしょう。
事業で使うために既に購入しているものもあれば、書き出してもらうといいと思います。
⑴-②運転資金
運転資金とは、実際に事業を継続していく際に必要となるものをいいます。
例えば、家賃とか材料の仕入や外注費などになります。これらについても、ざっくりと書き出してください。だいたい3か月分くらいを目安に書いてもらえればいいと思います。
①と②の合計額を一番下の合計欄に記載してください。
この合計金額が事業を行う上で初めに必要となる資金額になります。
この時点で多すぎるなと感じた場合には、設備資金の部分を中古の物に変更してみたり、精査してとりあえずいらないものは排除したりしてみてください。
どのくらいの金額が目安かというのは業種や業態・場所などによりますので、なんとも言えません。まず大事なのは書き出してみることです。書き出していても実際に事業を始めると必ず抜けているものがありますので、50万円~100万円はその他ということで多めに見積もっておきましょう。
⑵調達の方法
ここの調達の方法は比較的簡単です。
上の自己資金から順番に、左の合計額に揃うように入れていきます。
例えば、必要資金の合計額が1,000万円とすると、自己資金で500万円、家族からの借入が200万円とすると、日本政策金融公庫もしくは他の金融機関で必要な借入額は300万円となる。とこんな感じです。
ここで重要なのは自己資金+家族からの借入になります。必要資金額を全額金融機関からの借入で賄うことは不可能だと思っておいてください。3分の1から2分の1程度は自己資金+家族からの借入で賄えるようにしましょう。必ずそれくらいの自己資金が必要というわけではありませんが、自己資金があればあるほど有利ということになります。
金融機関も創業当初の会社にはあまりお金を貸したくないものです。なぜなら本当に返してくれるかどうかわからないからです。初めのうちは少ない金額から始まる、返済の実績を作っていくことで大きな金額を借りることができるようになるので、初めのうちは大きな金額が借りれなくても我慢しましょう。もしかすると大きな金額で借りれるかもしれないので、一度は融資に挑戦してみてもいいかもしれませんね。
⑧の欄は、創業時の全体的なバランスを見ている部分と思ってもらえればいいと思います。借入額が大きいということは、返済額も大きくなりますのでリスクが大きくなるという意味にもなってしまいます。創業時はできる限り少ない借入で創業できるように工夫してみましょう。
⑨事業の見通し(月平均)
ここの部分では、どれだけの売上・利益を上げることができるかを把握するところになります。
記載内容としては、売上・原価(仕入・外注費)・人件費・家賃・利息・その他になります。できる限り根拠と一緒に合わせて書いていきましょう。
創業当初は、創業3カ月目くらいの目安でいいと思います。創業してすぐの月から売上がない場合がありますので、3カ月目くらいまでで考えてもらう方が考えやすいと思います。
1年後又は軌道に乗った後の部分については、創業から1年後または軌道に乗った後の予測を書いてもらえれば大丈夫です。軌道に乗った後というのが非常に曖昧な表現ですので、何年後までいいの?と思うと思います。そのため、なるべく1年後を目安に書いてもらうのがいいでしょう。
⑴売上高
まずは、売上高になります。根拠と一緒に考えましょう。根拠の計算については業種によって様々だと思います。
例えば、飲食業や美容などのサービス業であれば「客単価×客数(一日の)×営業日数」で求めることができます。建設業などであれば「受注平均額×月の件数」で求めればいいと思います。労働集約的な業種であれば「従業員1人当たりの売上×従業員数」で求めてもらうのがいいでしょう。
⑵原価
原価については、売上高に対する原価率で求めてもらえればいいでしょう。ここで細かく計算する必要はないと思いますので、想定している原価率でざっくりと計算してもらえればいいと思います。
⑶人件費
人件費については、時給であったり日給であったりで計算してもらえればいいと思います。従業員を雇わない場合には0円で問題ありません。
⑷家賃
家賃については、賃貸する場合にはその賃貸料(1か月分)を記載してもらえればいいでしょう。
⑸支払利息
支払利息については、借入総額×利率÷12カ月で簡易に計算してもらっていいでしょう。本来であれば、「元利均等返済」か「元本均等返済」などで変わりますし、「元本均等返済」であれば毎月の利息額が変わりますが、そこまで細かく考える必要はありません。
⑹その他
その他の部分では、光熱費や消耗品費・税理士報酬などの他にかかると考えられる費用を記載しましょう。少し多めに書いておくのがいいでしょう。実際の事業を始めると想定しているよりも多くの金額がかかってきますので。
⑺利益
⑴~⑹を差引した結果が利益になります。
この利益で大切なのは、この利益から借入金の返済・税金の納付が行われますので、少なくとも借入の返済額よりも多い金額になっているか確認しましょう。個人事業主の場合は、個人事業主の生活費もここから捻出することになります。
この段階で利益がマイナスになっている場合には、見通しの内容や事業そのものの見直しが必要になるかもしれません。
借入金の返済額の求め方は「借入総額÷借入期間(月数)」でもとめることができます。この金額を利益が上回っていることが1番大切です。特に、1年後又は軌道に乗った後の方では、税金の納付(40%)を控除したあとでも借入金の返済ができるくらいの利益になっていることが望ましいと思います。
日本政策金融公庫の創業計画書の書き方のまとめ
⑧⑨の部分が創業計画書の中でもかなり重要な部分になってきます。ここの部分で不可能だと思う事業については、やめるか内容を変更するなど見直しをした方がいいでしょう。
日本政策金融公庫の創業計画書は非常に纏められておりシンプルな設計になっていますので、初めはとっかかりにくいかもしれません。しかし、最低限創業時に必要な考え方や考えておくことが纏められていますので、創業計画書を作成しておくことで頭の整理につながり、考えやすくはなるのではないでしょうか。
次回以降のコラムでは、私たちの事務所であるトラストソルコンサルティング(東憲吾税理士事務所)で使用している創業計画書の書き方について解説します。日本政策金融公庫の創業計画書を詳細にした感じになりますので、全体的に書き出すことができるのが特長になります。
書きやすい方の創業計画書を使ってもらうのがいいでしょう。
日本政策金融公庫の創業計画書→kaigyou00_190507b.pdf
