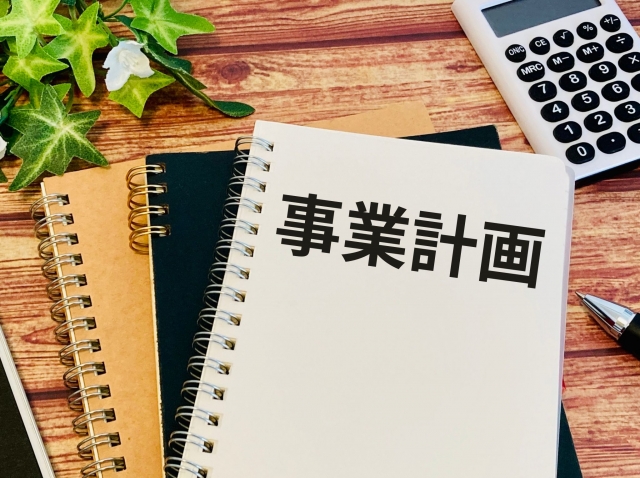
目次
⑶利益計画書の書く順番
利益計画を書く際の順番を説明していきます。
ここでいう順番とは、開業(売上が発生する月)後の書き方です。開業(売上が発生する)前については、仕入と経費(固定資産)の発生になりますので、支出した金額をそのまま書いていってもらえれば問題ありません。
では、順番なんてあるの?売上の上から順番に書けばいいんじゃないのと思うかもしれませんが、違います。違いますというよりは、売上の上から順番に書いていってしまうと、理想になり現実味があまりでないのです。
どこから考えていけばいいのか。どこから書いていけばいいのか。それは、下から順番になります。
まず、借入返済額と事業主給与(個人事業主のみ)を記載してください。この2つ(法人は1つ)の合計額が、最低限必要な営業利益になります。
この最低限必要な営業利益がスタートになります。最低限必要な営業利益が決まれば、最低限以上に必要な利益をプラスして営業利益を決めてください。
例えば、最低限必要な利益が10万円だとして、成長していくために後10万円利益が必要だとすれば、20万円ということです。これがスタートラインになります。
次に、毎月経常的に発生する経費を書いてください。地代家賃なんかは決まっているから書きやすいですよね。減価償却も右下の欄で計算されたものになるので決まっています。そのほかの想定される経費を書いていってください。
営業利益に、それらの経費を足し戻すと最低限必要な「売上総利益」がでると思います。
例えば、20万円の営業利益が必要だとして、毎月の経常的な経費が10万円かかるとすると、最低限必要な売上総利益は30万円ということになります。
この金額がその月に必要な粗利益(売上総利益)になります。粗利益(売上総利益)とは、売上から原価を引いたものであり、付加価値ともいわれるものです。会社全員で稼いだ利益といってもいいでしょう。企業の差別化の表れがこの粗利益になります。
この粗利益(売上総利益)が決まり、その額を粗利率で割り戻せば売上がでます。
例えば、飲食店だとして売上総利益が30万円必要で、平均原価率が40%だとすると、30万円÷(100%-40%)で50万円が最低限必要な売上ということが分かります。この計算で出た金額が営業利益20万円を達成するために必要な売上高ということになります。
この金額が現実的かどうかというのが大切です。これを売上から順番作成していってしまうと、かなり理想的なもの・調整したものになってしまいます。
最低限必要な営業利益から順番に下から考えていくことで、本当に必要な売上高を求めることができるのです。この時点で現実的かどうかが大事になります。現実的な数字でない場合には、経費の部分を見直すか原価の部分・売上の単価を見直すようにしましょう。
先ほどの例で、原価を40%から35%に見直したとするとどのように変化するでしょう。30万円÷(100%-35%)で46万円になります。原価率を5%見直せば、必要な売上高は50万円から46万円で済むようになります。
このように原価率の微妙な違いというのは非常に大事で、戦略にも大きく影響します。例えば、回転ずしと高級フレンチを考えてみてください。
回転ずしは、売価が低く原価は高い事業態だと思います。そのため利益を出すためには薄利多売なので、戦略としては数が必要となります。
これに対して高級フレンチの場合は、売価が高く原価は低いという事業態になりますので、高利薄売となり戦略としては、量より質という戦略になるのです。
このように、原価率の高い・低いは戦略にも関わってきますので、Part1・Part2で決めた戦略などと照らし合わせ、自分の事業はどちらの方がいいのかなどを考えていく必要があるでしょう。
利益計画まとめ
ここまでが利益計画の作成の方法になります。これを創業前から創業後まで1年から1年半分ほど書いてみてください。創業計画書の部分では、一月の区間でしかわからなかったものが、年間という流れで見えるようになったのではないでしょうか?
月によっては、利益が出る月もあれば出ない月もあっても問題ありません。事業には季節的な流れもありますし、繁忙期・非繁忙期はどのような業種にもあるためです。大事なことは年間で見た時にプラスになっているかが一番重要です。
利益計画書の営業利益のところがプラスになっているかどうかが第一です。
創業初期はマイナスになっていても仕方ありません。準備のための支出が多い可能性が高いためです。そのため1年から1年半の期間で書いてくださいと言っているのです。開業後(売上が発生してから)1年後にしっかりと営業利益が出ないような計画では、創業をしても仕方がありません。なんのために創業をするのかわからなくなってしまうほどです。よって、1年後にはしっかりと営業利益が出ているような事業計画・事業運営を考えていきましょう。
利益計画を作成することで、年間での流れを見える化でき年間での流れを想像しやすくなります。まずは、営業利益がプラスになっているか。そして、単月キャッシュフローの部分がプラスになっているかの順番で大切です。
キャッシュフローについては、次の資金繰り表の方が正確に表すことができますので、そちらを作成して確認していきましょう。
利益計画のポイントは下から順番に作っていくことです。営業利益から考えていきましょう。そして、経費は多めに売上は少なめに見積もるようにしましょう。
資金繰り表
⑴資金繰り表の書き方
利益計画に続いて資金繰表の作成の方法について解説していきます。
資金繰り表は利益計画をもとに作成してもらうのが簡単でいいと思います。
記載していく項目としては、売上・仕入・経費・利息・融資返済額・生活費(個人事業主のみ)を記載してもらうことになります。
①売上・仕入
まずは売上と仕入です。ここが一番難しい部分になります。記載する金額は基本的に合計額で構いませんが、回収・支払のサイトによって記載する月欄が変わることになります。
例えば、6月の売上で現金売上と30日サイトの売上があるとします。資金繰表に記載する際には、現金売上は資金繰表の6月の欄に記載しますが、30日サイトは7月の欄に記載することになります。これが利益計画表とのズレになります。ここの部分を気を付けてください。ここで間違うと全てズレてきてしまいます。
資金繰表の合計額が利益計画の合計額とズレてしまっても気にしないでください。ズレて当たり前ですので心配する必要はありません。
資金繰表は現預金の動きを見るための資料になりますので、税金を計算するための利益計画とは金額がずれるのが普通です。
②経費
経費の部分については、支出日ベースで記載してもらえれば問題ありません。例えば、人件費で6月分を翌7月15日払の場合には、利益計画では6月に書きますが、資金繰表では7月の欄に記載をしてください。基本的に支払日基準で書いてもらえれば問題ないです
経費の部分で利益計画と資金繰表でズレるのは、人件費・法定福利費がほとんどなのではないかと思います。
それ以外の細かい部分については、支払日ベースで書いてもらえればいいです。
資金繰表についても大きい金額については、正確に記載をしてほしいですが細かすぎるところは、ざっくりとで問題ありません。利益計画も資金繰表もおおよそを把握することが大切だからです。細かくこだわる必要はありません。質よりもスピードの方が大事です。なぜなら、あくまで予測であってその通りに物事は進まないからです。まずは、どの程度なのかを知ることが大切になってきます。
③利息
利息については、利益計画と記載される位置が異なるだけです。金額と月は同じになります。
④融資返済
融資返済額も利益計画の借入金返済額を同じ月・同じ金額でそのまま書いてもらえれば問題ありません。ここのために利益計画で記載していることになります。
⑤生活費(個人事業主のみ)
生活費についても、利益計画の事業主給与の金額を同じ月・同じ金額でそのまま書いてもらえれば大丈夫です。
⑥固定資産の購入
ここには利益計画で減価償却費の計算をした部分の金額を書いてもらいます。利益計画書の右下にかかる部分です。この固定資産の購入は、経費にはなりませんがキャッシュが出ていくものがあるからです。
例えば、借入をして購入したものであったり、分割で購入しているものも当てはまります。
一括で購入している場合には、月の欄に所得金額を書いてもらえればいいですし、分割で購入している場合には、分割払いの金額を毎月書いていってください。
ここの金額は減価償却費の金額とは同じになりません。固定資産の購入の仕方によって記載する金額が変わってきますので注意してください。
※ちなみにリースの場合は経費になりますので、経費の欄に記載してください。
⑦合計
①~⑥まで記載してもらうことで、合計の欄に数字が計算されると思います。
ここがマイナス(▲)であれば、現金支出の方が多いことを表し、プラスであれば現金収入が多いことを表しています。
経営では、利益計画のプラス・マイナスよりも資金繰表のプラス・マイナスの方が重要になってきます。
全て入力した後に、1カ月目の前期繰越の黄色の部分に自己資金の額を入れてみてください。この時点で翌月繰越の金額は増えていっていますか?ここが増えていっているのであれば問題ありません。現預金が増えていることになります。経営として問題なく進めていけるでしょう。
もしここで下がり続けていく場合には収益・支出の部分で問題があるということかもしれませんので、一度利益計画から見直しをしてみましょう。
⑵資金繰表の書く順番
続いて資金繰表の書く順番です。
資金繰表については、利益計画と異なり順番は関係ありません。利益計画をもとに上から順番に書いてもらえればいいです。
資金繰表については利益計画をもとに作成していきますので、簡単に書けます。逆に言うと資金繰表を書くためには利益計画が書けていないといけないということです。
まずは、利益計画を書けるようにしましょう。その後に資金繰表については、穴埋めみたいな感じですので、書きやすいと思います。
資金繰表のまとめ
ここでは、創業時の資金繰表の書き方について解説してきました。あくまで今回のコラムは創業をメインとしていますので、創業時の書き方について説明していっています。実際の事業が始まってからの書き方は少し変わってきますので、また別のコラムで解説することにしましょう。
資金繰表まで作成する事業者は10%程度といわれているので、資金繰表まで作成できればかなりのアドバンテージになるのではないでしょうか。利益計画と資金繰表を合わせてみて、創業後の事業がしっかり描けているか確認しましょう。
この段階で実現可能性があるのか肌感覚でわかると思います。実際の事業はやってみないとわかりません。何が正しくて何が間違っているのかは計画書だけではわからないのがほとんどです。しかし、ここで大切なのは肌感覚的に達成ができそうかどうかということです。これが肌感覚の時点で達成できなさそうであれば、利益計画から練りなおす必要があるでしょう。
なぜなら、計画上は1,000万円の利益が必要だとしても、肌感覚で売上が1,000万円くらいだと、その時点で達成の可能性が低くなると思います。計画の段階では肌感覚が重要です。やってみないとわからないですから。しかし、実現できそうと思ってやるのと、一か八かでやるのではリスクは全然違います。創業時にはあまり多きすぎりリスクはとらないように心がけましょう。
成長していく段階で勝負をしなければならないときが来ます。その時までは、しっかりと堅実に成長をしていくことが大切だと思います。
全体のまとめ
ここまでのコラムで、理念の部分や戦略の部分について考えてもらい、創業計画書の作成、利益計画・資金繰表の作成まで来ました。ここまでこれば書類的なものはほぼ完成でしょう。ここからが創業融資の融資を取りにいくというプロセスに進むことになります。どうでしょうか?創業って意外とめんどくさいなと思いましたか?
確かに色々考えないといけないことがあるので面倒くさいと思います。しかし、創業したいという夢を長続きさせるためには初めの計画が肝心だと思います。初めの段階で計画がある人とない人では雲泥の差がでるでしょう。
実際の中小企業で事業を行っているなかでも、計画書を毎年作成しているところは10%に満たないのです。どこも作ってないなら自分たちも作らなくてもいいやと思うかもしれませんが、この計画書があるのとないのとでは成長という意味で大きく変わります。計画書がある企業とない企業では圧倒的に計画書がある企業の方が成長している割合は多いでしょう。なぜなら何をしないといけないのか、どこを目指さないといけないのかが分かっているからです。わかっているから戦略を立てられるのです。
この計画書を作るという癖を創業の段階からしっかり持っていきましょう。企業として成長し、長く続いていくためにです。
次回のコラムからは創業融資に入っていきます。創業融資はどこに頼めばいいのか、どのような感じなのかを解説していければと思います。
それでは、また次のコラムでお会いしましょう。
