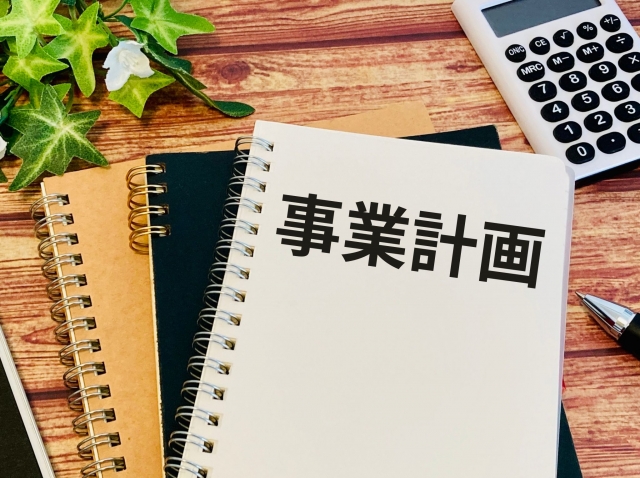
目次
初めに
前回・前々回では創業計画書の作成方法について解説してきました。今回のコラムでは利益計画と資金繰表の作成の仕方についてです。初めに、利益計画と資金繰表の内容について簡単に説明をしてから、前回コラムの⑦⑧であるトラスト流創業計画書の利益計画と資金繰表の作り方を紹介していきます。
今回の利益計画・資金繰表については創業時のみならず、通常時から作成することが望ましいものになりますので、作り方については覚えておいて損はありません。今後の融資の際にも必要となる知識になりますので、しっかり覚えていきましょう。
資料については、前回のコラムからダウンロード可能ですので、コラムを読みながら作っていけるように準備しておいてください。
それでは、本題に入っていきましょう。
利益計画と資金繰表
まずは、利益計画と資金繰り表の説明から行っていきます。もうすでに知っているという方については、飛ばしてもらって構いません。創業者向けのコラムになっていますので、一度内容についても説明を行おうと思います。
①利益計画
まずは、利益計画の方からです。利益計画は損益計画書ともいえるでしょう。利益計画では何をしていくのかといと、Part3・Part4でも作成したと思いますが、損益計画・事業の見通しの年間版を作るイメージを思ってもらえればいいです。
前回までのコラムでは、1月を切り抜いて損益計画・見通しを作成してもらったと思います。しかし、前回までに作成したものは、実際の事業が始まってから、もしくは一定期間を経過してからの部分を想定して作成してもらいました。
今回の利益計画では、創業前から創業後までの約1年半~2年間分を作成してもらいます。スムーズに創業に進める見込みがある場合にあは1年分くらいの作成で済むかもしれません。
つまり、創業前にかかる費用なども全て書き出して損益計画を作成してもらいます。
期間については、個人事業主の場合には1月~12月になりますし、法人の場合には決算月にしようと思っている月を一番後ろにもってきて、そこから前12カ月を書いてもらえれば大丈夫です。
利益計画では、創業前(実際に準備が始まる月)から創業後(一定程度軌道にのる月)までを一覧の表として作成してもらいます。そうすることで流れで利益がでるのかどうかを見ることができますし、年間を通じての数字も把握できるため利益を確認するという意味で使うことができます。
②資金繰表
続いて資金繰表です。これは利益計画書と似ていますが、少し違います。資金繰表は現預金の収支を見ていくための資料になります。利益とは関係がありません。資金繰表での書き方は、現金主義になりますので、入出金の月に記載していくことになります。
資金繰表の毎月の始まりは、前月の現預金の残高になり、毎月の終わりも現預金の残高となります。つまり、毎月の終わりの現預金残高がマイナスになるということは資金が足りないということを表すことになるため、マイナスにならないように資金調達や入出金の工夫が必要となります。
利益計画とどう違うのかというと、利益計画上では発生主義・実現主義の考え方で記載していくことになります。
例えば、6月30日締め7月30日入金100万円を記載する場合には、利益計画では6月の締め日を基準に記載しますので、6月の欄に100万円と記載します。これに対して資金繰表では、入出金ベースになりますので、入金がされる7月の欄に100万円と記載することになります。
同じものに対する金額であっても記載する欄が変わるということです。現金売上の場合には、利益計画と資金繰表は同じ月になりますし、サイトが30日を超える場合には資金繰表では利益計画の2カ月後の欄に記載するということになります。この原理を理解するのが一番初めは大変になり、頭の中がこんがらがってしまう要因の1つでもありますが、とても大切な原理になりますので、覚えておきましょう。
この原理を覚えておかないと利益では黒字がでているのに、現預金が足らずに倒産するという「黒字倒産」になってしまう危険性があります。利益が赤字であっても現預金があれば倒産しませんが、利益が黒字であっても現預金がなければ倒産するという原理を覚えておきましょう。
資金繰表というのがいかに大事なのかということが分かってもらえたと思います。
しかし、現実にはこの資金繰り表を作成していない中小企業がほとんどなのです。利益計画はするが資金繰表を作成しないという企業が多いのが事実ということは、資金繰表を作成するだけで銀行融資などの場面でアドバンテージ(有利)になるということでもあると思います。作り方を覚えてしまうと比較的簡単に作れるようになりますので、覚えておきましょう。
利益計画書と資金繰表の作成の仕方
それでは、作成の方法に入っていこうと思います。まずどちらから作るかということですが、利益計画の方から作成するようにしましょう。なぜなら発生主義で作成すること、利益を計算するものであることだからです。発生主義から現金主義を作成しないと作りにくいと思います。発生主義の資料を現金主義に直すのは、ずらせばいいだけですが、先に現金主義から作成してしまうと、売上が無理やり決定してしまうため矛盾が起こることになるからです。
まずは利益計画を作成。そして資金繰表に修正するという流れで作成していきましょう。
①利益計画(損益計画書)の作成方法
まずは利益計画から行きましょう。
創業時の利益計画の書き方としては、創業前と創業後に分かれます。創業前というのは売上が発生しない期間中に費用がかかる部分について考えます。創業後は創業(開業)して売上が発生する期間について考えます。すでに創業前で費用が発生しているものについても記載してもらって大丈夫です。
⑴利益計画の構造
利益計画の構造としては、売上・仕入(原価・外注費)・販管費(経費)・営業利益ここまでが日本政策金融公庫の創業計画書の見通しや前Partでも解説した損益計画の部分と同じです。
その後の償却前利益・事業主給与(個人事業のみ)・融資実行額・借入金返済額・単月キャッシュフローなどは、この後の資金繰り表を作成するための補完項目となっています。
実は、この利益計画だけでも簡易的な(発生ベース上)資金繰り表は作成できる仕組みになっているのですが、前章でも説明しているように発生ベースのため大きなズレが生じる可能性があるため、別途資金繰り表も作成してもらうのが良いでしょう。
そして、下の欄には飲食店等向けに客単価と客数で売上高を計算できるようにしています。ここの欄は使っても使わなくても構いません。この欄で計算したものを、創業計画書の計算根拠の欄に記載してもらうことも可能ですので、ここの欄については書くかどうかはお任せします。
⑵利益計画書の書き方
それでは利益計画書の書き方の説明をしていきます。
①売上・仕入
まずは、売上と仕入です。この2つについては考え方が同じなので、一緒に説明します。
売上・仕入ともに発生ベースで記載していきます。例えば6月の売上・仕入であれば6月の欄に書いてください。
ここでのポイントですが、サイト(入出金までの日数)が違うものを別の行に分けて記載することをおススメします。理由は次の資金繰表を作成するのを楽にするためです。
3行ほど用意していますので、例えば、(末締め・翌末入金)と(末締め・翌々15日入金)みたいな感じですね。その他の部分は、現金入金などの金額として比較的小さいものを想定してもらえればいいでしょう。比較的金額が小さいものについては、資金繰りでも影響がでないため現金取引とまとめてしまう方が楽です。あまり細かく考えすぎなくて大丈夫です。
仕入も同じように分けて記載しておくことをおススメします。
②販管費
ここの部分は、次の③固定資産を除いて基本的に必要なものを自由に記載してもらえれば大丈夫です。下の3行「減価償却」「支払利息」「その他」だけ残しておいてもらえれば、後は自由に記載してください。
書くものとしては、水道光熱費や地代家賃、広告費(HPの作成費・販促費)、人件費などになると思います。
人件費・地代家賃については金額が大きくなりやすいため、発生日ベースで書いてください。それ以外の金額が比較的小さいものについては、支払日ベースで書いてもらって構いません。資金繰りにも大きな影響はでないと考えられるためです。
支払利息の計算については、簡便的に「融資予定額×利率÷返済月数」で求めてもらえれば大丈夫です。利率について、その金融機関の平均的な利率の少し高めを見ておきましょう。創業融資を使用する場合には低い利率で記載されているところもあります。
③固定資産の購入
固定資産にはいくつかのルールがあります。今回は細かい解説はさけますが、10万円未満・30万円未満・30万円以上の3つにわけて軽く説明をします。書き方が変わってくるためです。
※固定資産とは、建物や改装費・車両運搬具・机などの備品・機械などと思ってください。
⑴10万円未満
固定資産の購入が10万円未満の場合には、即時経費にできますので、販管費の部分に記載して大丈夫です。
⑵30万円未満
固定資産の購入金額が10万円以上の場合には、固定資産として減価償却を行う必要がありますが、30万円未満の場合には一括で経費にできる特例がありますので、この場合も10万円未満と同様に販管費の部分に記載してもらって大丈夫です。
⑶30万円以上
固定資産の購入金額が30万円以上の場合には、減価償却ということを行う必要があります。減価償却とは簡単に説明すると、高額の固定資産を一括で経費にするのではなく、耐用年数に応じで何年間かに分けて費用化していく方法だと思ってください。利益の乱高下を防止するための処置だと思ってください。
30万円以上の場合減価償却をする必要がありますので、直接経費の欄に書くのではなく右下の部分に減価償却費を計算する欄を設けていますので、そこに一旦記入して下さい。
取得価額(見積書の金額)を書いてもらい、耐用年数を入れると自動で償却額(月額)が計算されますので、合計欄の金額を減価償却費という行に、開業した月から記載してください。
※あくまで簡易的な計算になります。
※耐用年数表については、国税庁のURLを載せておきますので探してください。
④償却前利益
償却前利益とは、営業利益に減価償却費を足した金額になります。なぜ足し戻しているのかは資金繰りのところにも関わるのですが、減価償却費とは現金の支出が伴わない費用になるためです。固定資産のところでも説明していますが、高額な費用を耐用年数に応じて各期間に按分して計上していることになっているだけで、現金を支払っているわけではありません。そのため営業利益に足し戻しています。つまりこの償却前利益がキャッシュ上の利益ということになります。
⑤事業主給与
ここは個人事業主の方のみ記載してください。生活にかかる費用・生活に最低限必要な金額を書いてください。ここは私生活においてどれくらい必要かを決めてもらえれば問題ありません。
⑥融資実行額
ここは融資予定額(決定額)を融資を受ける月(受けたい月)に記載してください。
⑦借入返済額
借入返済額は融資総額を借入月数で割った金額で大丈夫です。「元利均等返済」「元本均等返済」によって返済元本は違いますが、細かく計算するよりも大体でどのくらいのなるのかの方が大切ですので、「融資総額÷借入月数」で問題ありません。
⑧自己資金・保証金・設備支払
自己資金には、用意することが可能な自己資金額を書いてください。創業計画書の資金計画部分の自己資金額を書いてもらえれば大丈夫です。
保証金・設備資金支払には、③の固定資産の購入金額と賃貸物件の保証金を書いてもらえれば大丈夫です。ここも合計額で構いません。
④~⑦については、次の資金繰り表を書くのを楽にするための補完的なものですので、ざっくりとで大丈夫です。
次回へ続く。。。
